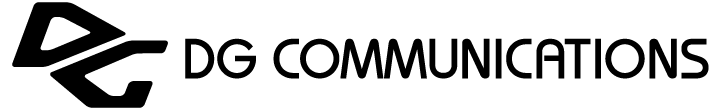株式会社デジタルガレージを創業した林 郁(代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO)と、伊藤 穰一(取締役 共同創業者)が、AI(人工知能)やユーザーインタフェースから、ブロックチェーン、バイオテクノロジーまで、先端技術の進化について語った。
林:AIからブロックチェーン、バイオテクノロジーに至るまで、技術進化がものすごいスピードで進んでいるけれど、Joiの目にはどのように映っている?
伊藤:「どうすればみんなが幸福になるのか」に主眼をおいて、先端技術を活用することを意識すべき時代になったと思う。ITがこれだけ浸透しても実は人間の生産性は上がっていないという説もある。実は、森の中を自由に走っていた古代人の方が、現代人よりも幸せだったのかもしれない。これからは、単にスピードや効率を上げるだけではなく、真の意味でみんなが豊かな生活を送るために技術をどのように活かすかを考えることが、デジタルガレージが掲げる「世の中の役に立つ事業の創出」に直結する。社会とか都市のレベルで俯瞰することも必要だと思う。
林:AIが社会にもたらす影響やそれに伴う倫理問題も、人間の幸福感と密接な関係があるね。
伊藤:AIの進化によって人間がいらなくなってしまうかも知れないといった問題は、日本よりもアメリカの人たちの方が気にしている。自動運転が実用になると人間とAIの関係はどのようになるのか、AIがドライバーを補助するドライブアシストと完全自動運転の間のどこにちょうど良いバランスが取れるところがあるのか、といったことを議論している。重要なのは、人間と機械のインタフェースをうまくデザインすることで、人間と機械が助け合って活動するようなプロダクトを作ることだと思う。

林:ファクシミリが登場した時には「新聞配達は過去のものになる」と言われたし、銀行ATMができたら「銀行員がいらなくなる」と言われていた。でも結局変わらなかった。同じようなことがAIにも言えるような気もするけれど。
伊藤:会社を例にとると、大企業はすでに一人の人間が理解できる範囲を超えた複雑なシステムになっている。そのシステムを構成する要素としてすでにAIがいくつも組み込まれ始めている。裁判官にしても、パイロットにしても、お医者さんにしても、判断にAIの助けを借りることが当たり前になっている。株の売買だって実際はコンピューターがアルゴリズムに従って行っているのがほとんど。そう考えると、いつの間にかAIがさまざまな場面で人間の判断を補助するようになっているのが現状と言える。もはや、AIは世の中で起こっている進化を加速する原動力になっている。だから、人工知能の進化の方向が間違っていたら、社会を間違った方向に加速させてしまう。社会そのものが正しい方向を向くように、人工知能の進化を導いていく必要がある。
林:鍵を握るのは倫理観や価値観のデザインになるね。
伊藤:今は日本でも、モノがあればあるほど幸せになるという価値観が普通になっているけれど、昔は、必要以上のモノはなくていいとか、自然と人間は平等という価値観が当たり前だった。自然をコントロールして人間に役立てるという西洋的な価値観のまま、そこにAIが入ってくると自然環境がボロボロになってしまう恐れがある。それを今一番危惧している。
個人の利益を優先させるか、社会全体の利益を優先させるかという問題に置き換えることもできる。自動運転にしても、個人と社会のどちらを重視するかによって設計思想が全く異なる。MITメディアラボのLyad Rahwan氏の研究によると、ドライバーを犠牲にしてでも大勢の人を救う判断をする自動運転車の是非について一般の人に意見を聞くと、「倫理的には正しいが、自分は絶対に買わない」という声がほとんどらしい。つまりマーケットに任せると、周りよりもドライバーの命を優先する車ばかり世の中に増えることになる。それは社会的には良いことではない。社会全体の利益に資する方向で技術開発を進める必要性がある。
林:2020年くらいから普及が始まる5Gネットワークは、自動運転にどう影響を与えるだろう。 日本メーカーの強みは生きるのだろうか。
伊藤:アメリカでは、例えばテスラがセンサー技術を駆使して自己完結型で自動運転を実現しようとしているけれど、社会の利益を優先するには、例えば5Gネットワークを使って全部の車が互いにコミュニケーションをとり、オーケストラのように協調するような仕組みを採ったほうがいいかもしれない。「和」を尊ぶ日本メーカーの強みが生きそうだ。そんな日本文化に根ざしたプロダクトが世の中に出てくるといいと思っている。
ユーザー本位のサービス開発を
林:デジタルガレージは、全日空グループと合弁で決済会社を作って、空港に実験的なショッピング手法を提供することを検討している。近未来のショッピングについてどのようなイメージを持っている?
伊藤:プライバシーと広告の関係への配慮が重要で、アマゾンもそこにすごく気をつけている。ユーザーの立場だと有益なレコメンドは便利なので欲しいけれど、自分の情報が外に漏れるのは避けたい。信用のあるブランドが個人情報をきちんと管理して、その人にあったショッピング体験を提供するというのが現実的かもしれない。オンラインショッピングと実店舗でのショッピングをシームレスにつなぐことも重要になりそう。どの店に入ったら自分の好きなものがあるかは知りたいけれど、自分のに関する情報をいろいろな所にばらまくことは避けたいというのが人情。セキュリティとレコメンデーションをうまくバランスさせないといけない。
デジタルガレージも、広告代理店としての事業を行っているので、加盟店とプロダクトとユーザーの情報をうまく管理するための技術開発を進めるべきだと思う。例えば最新の暗号技術を活用して、ある瞬間だけユーザーの嗜好に関するデータへのアクセスを許可するとか、細かい情報は伏せて必要な情報に絞ってデータを開示するとか、いろいろな手法が考えられる。
林:アマゾンが、高級スーパーを展開するホールフーズを買収したのはどう分析する?
伊藤:アマゾンとグーグル、フェイスブックの中で、創業者がビジネスプランを書いて作ったのはアマゾンだけなんだ。グーグルもフェイスブックも、とりあえず何かを作りながら考える形で事業を拡大してきた。今のマネジメント手法にもそれは影響を与えていて、アマゾンはトップが明確な戦略を持っている。ホールフーズの買収も綿密な計画に沿ったものだと思う。だからアマゾンはこれからもジリジリ伸びていくだろう。
林:今はスマートフォンがオンラインの入り口になっているけれど、その先のユーザーインタフェースはどうなっていくだろう。アマゾンのアレクサとか、グーグルホームはどのように進化していくと思う?
伊藤:Mixed RealityとかAugmented Realityと呼ばれるいわゆる「拡張現実」がアメリカでは注目を集めている。現実世界の映像と仮想世界の映像を重ね合わせて表示する技術だ。アレクサやグーグルホームのような音声インタフェースの普及も進むだろう。現実世界と仮想世界をビジュアルと音声によってつなぐ分野は、これからスタートアップがどんどん出てきそうだ。
林:音声インタフェースを備えた機器には、家の中で聞き耳を立てているようなイメージを抱く人もいるようだが、プライバシーの心配は。
伊藤:サービスを提供する会社としては、信用を失ったらそれまで築いてきた価値がゼロになるくらいの覚悟をしている。この前も、FBIがある人物を対象とした犯罪捜査のために、その人が使っているアレクサの情報を提出するようにアマゾンに要求したが、アマゾンは断った。アップルもiPhoneに格納した個人情報を巡ってFBIと戦った。つまりアメリカの企業は政府と戦ってまで、顧客からの信用を守らなければならないと考えている。日本のメーカーもこうした姿勢を参考にすべきだと思う。
林:ARやVRの普及はどのように進んでいくだろう。
伊藤:VRはエンターテインメント分野で浸透していくと思う。ARにはさまざまな用途がある。メガネ型でなくても、スマートフォンだけでも十分楽しめる。メガネ型のARデバイスを普及させるにはデザインがカギを握ると思う。かっこ悪いものを顔につけたがる人はいないから。その壁を乗り越えないと、新しい分野のプロダクトを広めることは難しい。
林:個々のユーザーに合わせて対話するインタラクティブエージェントは、ここ数年で新しいユーザーインタフェースとしての市民権を確立するだろうか。
伊藤:単にユーザーからの指示に応えるようなエージェントではなく、ユーザーの状態を把握し先回りしてアクションをするエージェントが主流になっていくと思う。頭の中で意識していること以外に、人間の体の中ではいろいろなことが起きている。こうしたたくさんの情報を統合して、ユーザーに最適なサービスをするエージェントが望まれるだろう。例えば体温が上がって汗をかいていることを検知すると部屋の温度を下げてくれるとか、血糖値が下がったらジュースを出してくれるとか。街全体が一つのエージェントとして働くような生活環境が登場するかもしれない。
林:まさに「スマートシティ」だね。2020年の東京オリンピックに向けて、渋谷など、日本でも新しい都市空間を作る動きが活発になってきている。Joiの描く理想の街は?

伊藤:住んでいる人が気持ちいいことが大切だと思う。僕にとって気持ちのいい街は、歩いていける場所に何でもあること。例えば、カフェとかお菓子屋さん、薬局などが満遍なく点在しているパリ。美術館に行くには交通機関に頼る必要があるけれど、普段の生活に必要なものは徒歩圏内で調達できる。日本の街づくりもそれに近い。一方でアメリカの大都市は、住宅街、金融街といった具合に機能ごとに街が分かれていて、徒歩だけでは生活しづらい傾向にある。MITメディアラボは、中国などで街づくりのプロジェクトも手掛けている。
黎明期のFinTech、活気付くバイオ
林:Joiは金融庁のアドバイザーをやっているけれど、FinTechの現状についてどう思う?
伊藤:日本に限らずFinTechはまだ黎明期だと思う。インターネットの歴史に重ね合わせてみると、今のFinTechはインターネットが標準化される前の段階。キャプテンとか通信会社があって、光ファイバーからコンテンツまで全部自前でやらないといけない世界。イーサーネットの規格すらまだ決まっていない状況だと思う。IPプロトコルが決まると、シスコのようなルーティングをする機器の会社が登場して爆発的に伸びる。FinTechの世界でも、DGが出資しているBlockstreamなど、先進的なスタートアップが生まれてきている。こうしたスタートアップの取り組みによってブロックチェーン関連などの業界標準などがまとまっていくと、FinTechは社会のインフラを支える大きな存在として認識されるようになる。
林:歴史的にみると技術的に筋が良いからといって、必ずしも大成功するとも限らないのも事実だね。
伊藤:インターネットの黎明期にも、いろいろな技術が業界標準を巡って戦っていた。X.25とかIBMのトークンリングとか。インターネットが証明したのは、一番優秀な人たちが集まるコミュニティがあって、オープンにやりとりしていたところが一番伸びるということ。だから、MITメディアラボでもオープンなコミュニティを作ることを意識している。FinTechの抱える問題は、スタートアップ企業にお金が集まりすぎていて、優秀なエンジニアがそちらに流れていること。大学や非営利のオープンソースコミュニティの人材が不足している。今の状態がややバブルになっているのが心配。
林:バイオテクノロジーの進化も加速している。
伊藤:世界トップクラスの囲碁名人を破ったAI「AlphaGo」を開発したディープマインドのトップ2人がもともとは脳科学の研究者だったように、バイオテクノロジーとコンピューターサイエンスの融合がどんどん進んでいる。MITメディアラボでもコンピューターサイエンスのバックグラウンドを持つ優秀な人たちが、バイオの領域に進出し始めている。その結果、創薬といった典型的なバイオの分野にデジタルの考え方が入ってくるのと同時に、素材とか建築、デザインといった分野にバイオから学んだものが応用されるようになった。プログラミングを覚えないとコンピューターサイエンスが分からないのと同じように、バイオテクノロジーを理解しないとAIや建築が分からないという時代になってくると思う。だから今の子供達はバイオを勉強すべきだし、インターネットの波に乗り遅れた企業が淘汰されたように、企業の経営者もバイオテクノロジーの方向性をある程度理解しておかないと、時代に取り残される可能性がある。
林:近代建築が出てきた時のアーキテクトの思考に似ているね。
伊藤:メタボリズムの時代は、バイオのアイデアを建築が取り入れていったけれど、当時はまだバイオと建築の技術が相互に乗り入れるところまで進んでいなかった。今は、例えばバイオテクノロジーで自然原料から蜘蛛糸のような素材を大量生産して、それを元に自動車の部品を作るといった動きが現実になっている。こういう世界を普通に想像できるようにならなければいけない時代になっている
林:地球が何十億年かけて培ってきたものを、人間の意思でハンドリングできるようになりかけているわけだ。デジタルガレージも、こうした大きな時代の変化を先取りしてグローバルな視点で社会に貢献する事業を作っていきたい。
- DGコミュニケーションズ >
- 未来を支える技術は今どこまできているのか?林 郁×伊藤穰一対談